奈良市を訪れたことがある方は、街中に鹿があふれているのを見たことがあることでしょう。
奈良市内にいる鹿は特別天然記念物として大事に保護されています。
奈良市中心部は元々春日大社の神域であり、春日大社における神の使いが鹿であるからです。
では、どうして春日大社の神の使いは鹿なのでしょうか?
調べてみると表に出ていない隠された理由がありそうです。
春日大社とは?
奈良市にある神社で藤原氏の氏神としても有名です。
全国にある春日社の総本社です。
祭神は武甕槌命(タケミカヅチ)、経津主命(フツヌシ)、天児屋根命(アメノコヤネ)、比売神(ヒメガミ)とされています。
タケミカヅチとフツヌシについては、国譲り神話で大国主から国を奪うのに活躍した戦の神として有名ですね。
武道場などに「鹿島大明神」と「香取大明神」と書かれた掛軸が並んでいるのを見たことがありませんか?
タケミカヅチが祀られているのが鹿島神宮でフツヌシが祀られているのが香取神宮で、いずれも今の茨城県にあります。
アメノコヤネは藤原氏の祖先神とされ、天孫降臨の際にニニギノミコトに同行した神です。
ヒメガミは春日大社の場合はアメノコヤネの妻であるとされていますが、別の神社ではアマテラスを指すとも、宗像三女神を指すとも言われています。
一般的には機織りの神として祀られています。
鹿との関係とふたつの神宮
春日大社の公式HPによると、タケミカヅチが東国にある鹿島神宮から白い鹿に乗ってやって来たので、神の使いになったということです。
鹿島神宮は香島神宮とも表記されます。
伝説では神武天皇の時代に創建されたという由緒ある神社です。
藤原氏の初代は中臣鎌足ですが、その父は鹿島神宮の神職だったという説があり、鎌足自身も鹿島出身という説もあります。
なお、同じ茨城県には香取神宮というこちらも由緒ある神社があり、こちらの祭神はフツヌシです。
戦の神である両者が近い土地に神宮という高い扱いで存在していることから、このあたりは東国支配の根拠地であったという説が有力です。
なお、明治以前に神宮と呼ばれる格の高い神社は3つしかなく、伊勢神宮、鹿島神宮、香取神宮の3つです。
いかに両神宮が特別な存在だったかわかります。
謎多き神、安曇磯良
話は少し逸れますが、安曇磯良(アズミノイソラ)という神様がいます。
名前を聞いてもなかなかピンと来ないかもしれませんが、海人族の神に当たる存在です。
実在した人物ではないかとも見られています。
安曇氏の祖先とされ、安曇氏は安曇野、熱海、渥美などの地名の由来となったとも言われています。
神功皇后が三韓征伐に赴く際、協力した存在ともされています。
また「君が代」は元々このアズミノイソラのことを讃えた歌だという説もあります。
このアズミノイソラの根拠地だったのが、今の福岡県にあり、海に突き出した陸繋島である志賀島(しかしま・しかのしま)です。
ここには現在も志賀海神社が存在しており、アズミノイソラらを祀っています。
志賀島は「漢委奴国王」の金印が発見された場所でもあります。
金印については後世に作られた偽物という説もありますが、いずれにせよ、古代から志賀島もアズミノイソラも重要な存在だったと考えられます。
朝廷の祖先が大陸から渡って来たとするなら、必ず海を支配していた存在と対決か協力をする必要があったことでしょう。
残された伝説から考えて、自発的か強制されたのかはわかりませんが、アズミノイソラは朝廷の祖先に協力したと考えるのが自然です。
志賀島=鹿島?武甕槌命=安曇磯良?
志賀島は「しかしま」または「しかのしま」と読むわけですが、鹿島という名前を見れば、こちらも同じように読めるのがわかりますね。
志賀島を根拠地とし、朝廷の祖先に協力したと見られるアズミノイソラ。
このことからタケミカヅチの神と同一視することが可能です。
牽強付会と思われるかもしれません。
ですが、例えば「琉球神道記」という文献には、「神皇正統記」からの引用と断りながら、以下のような記載があります。
「鹿島明神はもとはタケミカヅチの神なり。人面蛇身なり。常州鹿島の海底に居す。一睡十日する故に顔面に牡蠣を生ずること、磯のごとし。故に磯良と名付く。神功皇后、三韓に征し給う時に九尾六瞬の亀に乗りて、九州にきたる。勅によりて、梶取となる。
また筑前の鹿の島の明神。和州の春日明神。この鹿島。同じく磯良の変化なり」
また、傍証として諏訪大社で行われる祭りで、御頭祭(おんとうさい)というものが挙げられます。
これは鹿の頭を75個、神様への貢物として捧げる祭りです(現在は剥製で代用)。
この諏訪大社の祭神は建御名方(タケミナカタ)です。
大国主命の息子のひとりで力自慢でしたが、タケミカヅチに敗れて、諏訪まで追いやられ封じ込められた神様です。
この神社で鹿の頭を75個も捧げるというのは、余程、鹿に対して恨みがあるということでしょう。
鹿に関係する神様といえば、鹿島神宮と春日大社に祀られているタケミカヅチということになりますし、鹿島の語源が志賀島となると、タケミカヅチ=アズミノイソラという図式が成り立ちます。
まとめ 彼らもまた怨霊?
表向きは神の使いとして手厚く保護されている鹿ですが、鹿がタケミカヅチやアズミノイソラとつながるなら、朝廷の祖先に利用された存在と言えなくもありません。
おそらく東国を支配して行く尖兵として海人族は利用されたと考えられるのではないかと。
そして、用が済めば……
日本では古来より恨みを持って亡くなった人々を神として手厚く祀り、怨霊を鎮める方法が取られています。
オオクニヌシと出雲大社、菅原道真と北野天満宮……
鹿島神宮や香取神宮が神宮として他の神社より格の高い扱いを受けていることも傍証と言えます。
神の使いとされる鹿ですが、真相は神(この場合は朝廷や藤原氏)に利用された海人族の人々を表しているのかもしれません。
余談・比売大神と伊勢神宮について
明治以前は3つしかなかった神宮。
鹿島と香取以外では伊勢神宮となるわけですが、祭神のアマテラスは機織りの神様でもあります。
なお、同じ茨城県に常陸国二ノ宮として知られる静神社という神社があります。
祭神は建葉槌神(タケハヅチ)という神様で機織りの神様としてアマテラスに仕えた存在と伝えられています。
古代、常陸国は織物の産地だったようです。
アマテラス自身も機織りの神様であることから、このタケハヅチも、もしかすると……
また、アマテラスを卑弥呼と同一視する説があります。
卑弥呼に仕えた存在となると、後継者の台与(壹与)という想像もできるのですが、ここまで飛躍するとキリがありませんので、このあたりで止めておきましょう。
しかし、春日大社にも比売神が祀られているのは、もしかすると、タケミカヅチ、フツヌシと共に利用された存在として並べられている可能性も捨てきれません。
↓参考文献
この本の紹介は以下の記事にて行っています。



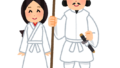

コメント