新喜劇の重鎮、元は漫才師
「ごめんください。どなたですか……ありがとう」
「神様〜!」
などのギャグで知られる吉本新喜劇の重鎮、桑原和男さんはかつて「原あち郎・こち郎」というコンビ名で漫才をしていました。
こち郎が桑原さんです。
コチ郎というカタカナ表記だったという説もあります。
本名は九原一三(くはら・かずみ)。
1936年2月23日生まれ。
北九州小倉の出身で、親は漁師でした。
本人も漁が好きで幼い頃から親について漁に出ていたそうで、将来は漁師になるかなと思っていました。
しかし、船酔いをする体質だったらしく、断念したというオチがついています。
いとし・こいしに弟子入り
一時、小学校の教師を目指した時期もありましたが、漫才師に興味を持ち、「漫才の教科書」とまで呼ばれた名コンビ、夢路いとし・喜味こいしのふたりに弟子入りします。
いとし・こいしのふたりは「弟子が師匠と同じ漫才をしても意味がない」と、弟子を取らない主義でした。
しかし、中学卒業時に弟子入り志願してきた桑原少年に「高校出たらまたおいで」と言ってしまいました。
※実際会ったのではなく、弟子入り志願の手紙を送ったら、返事がそうだったという説もあります。
「まさか来ないだろう」と思っていたら、三年後、本当に来てしまったため、断れなくなって弟子にしたというエピソードが伝わっています。
漫才師としては三度のコンビ別れを経験し、ひとりの方がやりやすいと喜劇役者に転向します。
吉本新喜劇で活躍
その後、紆余曲折の末、吉本新喜劇の前身である吉本ヴァラエティに入団。
芝居の才能に目覚めることとなり、新喜劇の大御所と呼ばれるほどの存在となりました。
芝居が大好きで、年に3日くらいしか休むことがないほど、舞台に立ち続けていました。
小柄だったのと、優しい顔立ちだったことから女性役を演じるようになり、「和子のおばちゃん」はハマリ役となります。
時折、他の劇団員と漫才コンビを組み、地方公演などで演じることはあったそうです。
しかし、超一流漫才師唯一の弟子であるというのに、漫才で活躍できなかったことを申し訳なく思っていると語ってもおられます。
恩返しを提案
のちにいとし・こいし師匠の話芸が大阪市無形文化財として表彰されることとなりました。
その際「師匠のおかげで私も洋服を買えるような身分になれました。授賞式に着ていく服を恩返しにあつらえさせてもらえませんか?」と提案したものの「弟子が余計な心配せんでええ」と断られたとか。
断ったものの、その気持ちはうれしかったと喜味こいし師匠は著書に書いています。
人生の最期は本名で終えたい
いとし・こいし師匠も鬼籍に入られ、桑原和男さん自身も高齢となりました。
人生を終了するときは「桑原和男」という芸人としてではなく、本名の「九原一三」というひとりの一般人として終えたいという考えを持っているということです。
2023.0810追記
老衰のためお亡くなりになられました。
享年87歳。
九原一三さんとして最期を迎えることができたのでしょうか……
ご冥福をお祈りします。
余談・池野めだかも元漫才師
ちなみに同じ吉本新喜劇で活躍中の池野めだかさんも、元々は漫才師で、「海原かける・めぐる」というコンビを組んでいました。
月亭八方は未だに池野めだかのことを「めぐるくん」と呼んでいます。
なお、このときの相方、海原かけるは「海原やすよ・ともこ」の父です。



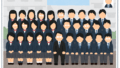
コメント